

カンファレンスとは?分野別・目的別のカンファレンスの意味と使い方
カンファレンスとは、「比較的大規模な会議」という意味です。
ただし、カンファレンスが様々な意味を持っているために「わかりにくい」と感じてらっしゃるのではないでしょうか。
実は、カンファレンスの意味は場面によって異ります。例えば、医療とビジネス、スポーツそれぞれの分野で「カンファレンス」の意味が異なるということです。
そこでこの記事では、一般的なカンファレンスの意味だけでなく、分野別のカンファンスの意味まで解説していきます。
また、病院で働く看護師のために「病院で行うカンファレンス」を目的別に区分して解説していきます。
ビジネスパーソン、医療従事者問わず、「カンファレンス」の意味をはっきり理解したい人のためにまとめましたので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
目次
- 1 カンファレンスとは
- 2 カンファレンスが使われる主な3つの場面
- 3 カンファレンス、ミーティング、ディスカッションの違い
- 4 医療の現場で使われる16のカンファレンス:目的別分類
- 4-1 【チームカンファレンス】チーム医療の連携・質を高めることを目的とする
- 4-2 【術前・術後カンファレンス】安全に手術することを目的とする
- 4-3 【ケアカンファレンス】複数職種間での情報共有・問題解決を目的とする
- 4-4 【ウォーキングカンファレンス】患者さんの参加を目的とする
- 4-5 【入院カンファレンス】治療の大きな方針共有を目的とする
- 4-6 【退院前カンファレンス・地域カンファレンス】スムーズな社会復帰を目的とする
- 4-7 【デスカンファレンス】亡くなった患者さんを振り返りと今後のケアの活用を目的とする
- 4-8 【臨床病理カンファレンス】臨床経過と疾患の本態との関連を総合的に理解することを目的とする
- 4-9 【オープンカンファレンス】知識の蓄積・交流を目的とする
- 5 延長しがちなカンファレンスを早く終わらせる2つのコツ
- 6 まとめ:カンファレンスごとに目的を理解しよう!
1 カンファレンスとは
カンファレンスは、「会議・協議会」「連盟・同盟」といった意味を持ちます。
前述した通り、カンファレンスの意味は分野によって微妙に異なります。例えばビジネスやスポーツ、医療など、それぞれの分野で「カンファレンス」が指す意味が微妙に異なります。
次から分野別のカンファレンスの意味を解説していきます。
ポイント
カンファレンス(conference)は「コンファレンス」「カンファランス」ともよばれることがありますが、発音のしかたが微妙に異なるだけですべて同じ意味合いをもっています。この3つの表記のなかでは「コンファレンス」が最も英語(conference)の発音に近いとされていますが、日本では「カンファレンス」と表記されることが一般的です。
2 カンファレンスが使われる主な3つの場面
カンファレンスは3つの場面に応じて、微妙に意味が異なります。
- 医療
- ビジネス
- スポーツ
それぞれ解説していきます。
2−1 医療におけるカンファレンス:小規模な会議・打ち合わせ・話し合い
医療現場におけるカンファレンスは、「会議・打ち合わせ・話し合い」といった意味で用いられます。
患者さんに関する情報をそれぞれの担当者が報告し、メンバーどうしで協議しながらよりよい医療ケアを提供することを目的として行われています。
テーマや参加者、目的に応じてさまざまな種類のカンファレンスが日常的に開かれており「カンファレンス」という言葉もよく使用されるため、職場によっては「カンファ」と略されることも少なくありません。また種類も多いため、たとえばリハビリについてのカンファレンスは「リハカン」といったような略し方をする職場もあります。
実施されるカンファレンスの種類は職場によって異なります。自分の職場ではどのようなカンファレンスが行われており、自分が参加するカンファレンスがどのような目的で行われているかを知ることが重要となってくるでしょう。
医療におけるカンファレンスは「数人~十数人規模のものから数十人以上の規模の会議」を指すことが多いです。
2−2 ビジネスにおけるカンファレンス:大規模な会議
ビジネスシーンにおけるカンファレンスは、「会議」の意味で使われます。
医療の現場では「打ち合わせ」や「話し合い」という意味が含まれますが、ビジネスシーンでは含まれません。「経営カンファレンス」のようにあらたまった場で使われることが多いです。
少人数の会議よりも、大人数の会議のことをカンファレンスと呼ぶことが多いです。
「数十名〜数百名のような比較的規模の大きい会議」を指すことが多いです。
2−3 スポーツにおけるカンファレンス:連盟、同盟
スポーツ分野におけるカンファレンスは、「連盟」「同盟」という意味で使われます。
「イースタンカンファレンス」や「ウエスタンカンファレンス」のような使われ方です。つまり、いくつかのスポーツチームで構成される「リーグ」のことをカンファレスと呼びます。
前述した医療やビジネスでの使われ方(意味)とは大きく異なります。
3 カンファレンス、ミーティング、ディスカッションの違い
医療の現場では「会議」や「話し合い」といった意味をもつ「カンファレンス」という言葉ですが、似たような意味をもつ言葉に「ミーティング」や「ディスカッション」があります。
それぞれの違いは下記の通りです。
| 言葉の意味 | 話し合いの規模 | 話し合いの内容の例 | |
| カンファレンス | 会議・会合 ※医療分野:話し合い・情報共有 | 数十人以上 ※医療分野:数人規模のケースもあり | ・重要事項の話し合い ・情報共有 ・問題解決のための議論 |
| ミーティング | 会議・打ち合わせ | 数人~十数人程度 | ・打ち合わせ ・情報共有 ・仕事の進捗確認 ・引継ぎ事項の確認 |
| ディスカッション | 討議・討論 | 数人~十数人 | ・問題解決のための議論 |
3-1 カンファレンス
「カンファレンス」は医療分野では「会議」「話し合い」という意味合いが強く、ビジネス分野では「大規模な会議」を指すことが多いです。
医療分野では数人~十数人程度の場合でもカンファレンスというのに対し、ビジネス分野では少なくとも出席者が数十人以上となる正式な会合をカンファレンスとよびます。
3-2 ミーティング
カンファレンスは一般的に「規模の大きい正式な会議」を意味しますが、「ミーティング」は比較的少人数で行われる会議のことを指しています。
ミーティングは「打ち合わせ」と訳されることもあり、医療の現場では看護師の申し送りなどがミーティングに相当するでしょう。
3-3 ディスカッション
また「ディスカッション」は「討議・討論」という意味があり、比較的小規模な話し合いを指しています。ミーティングが進捗状況や引継ぎ事項の確認を行う場である一方、ディスカッションは議論を行い問題を解決することを目的として開かれます。
「議論すること=ディスカッション」であるため、カンファレンスのプログラムに組み込まれていることも少なくありません。
医療の現場では「カンファレンス」を用いる機会が多いと思いますが、ビジネスの場における「カンファレンス」とは少し意味合いが異なります。類語もあわせて確認し、シーンに応じて使い分けられるとよいでしょう。
4 医療の現場で使われる16のカンファレンス:目的別分類
医療の現場では目的に応じてさまざまな種類のカンファレンスが行われています。カンファレンスに参加する際には、目的や参加者を確認し、自分の役割をきちんと意識しておくことが大切です。
では、医療現場で開かれているカンファレンスにはどのようなものがあるのでしょうか。主なものを簡単に確認していきましょう。
- チームカンファレンス(多職種カンファレンス、合同カンファレンス、病棟カンファレンス)
- 術前・術後カンファレンス(手術室カンファレンス、オペカンファレンス)
- ケアカンファレンス
- ウォーキングカンファレンス
- 入院カンファレンス
- 退院前カンファレンス・地域カンファレンス
- デスカンファレンス
- 臨床病理カンファレンス
- オープンカンファレンス
4-1 【チームカンファレンス】チーム医療の連携・質を高めることを目的とする
チームカンファレンス(多職種カンファレンス、合同カンファレンス、病棟カンファレンス)とは医師や看護師、薬剤師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士などさまざまな職種のスタッフが1つのチームをつくり、治療の指針について話し合うことを目的としたカンファレンスです。
病棟単位で行われる場合は「病棟カンファレンス」、支援のなかでも1つの分野に焦点をあてる場合、たとえば栄養分野にフォーカスしたカンファレンスである場合は「栄養カンファレンス」などとよばれることもあります。
チームカンファレンスは「患者さんに対する最善のサポートを考えること」が主な議題です。患者さんと接する機会の多い看護師はカンファレンスでも重要なポジションとなるでしょう。チームカンファレンスをより有意義なものにするためにも、日ごろから患者さんの身体状態や心理状態、気になることなどを整理しておくことをおすすめします。
4-2 【術前・術後カンファレンス】安全に手術することを目的とする
術前・術後カンファレンス(手術室カンファレンス、オペカンファレンス)は手術の前後に行うカンファレンスです。
手術前の患者さんの病態や状態、患者さんから聞き取った情報(アレルギーや既往歴)といった情報をもとに担当医師や手術の補助を行う看護師、麻酔科医師、薬剤師など、手術に関わる医療スタッフが話し合い、安全に手術を行うことを目的として開かれています。
術前・術後カンファレンスでは、看護師は手術室での流れや安全面に関することの説明を行います。また患者さんの看護計画を関係者に周知することも大切な仕事です。
4-3 【ケアカンファレンス】複数職種間での情報共有・問題解決を目的とする
医療現場におけるケアカンファレンスとは、患者さんのケアに関する話し合いを指しています。
医師や看護師、作業療法士、薬剤師、ケアマネジャーなどといった複数の職種に加えて患者さんやそのご家族も加わり、今後行っていく治療や処置の内容、入院中の計画について情報共有することが目的となります。
また病院だけでなく介護施設でも同様のケアカンファレンスが行われています。介護施設でのケアカンファレンスに看護師として参加する際には、自分がもっている看護に関する知識やスキルと施設でも可能なケアをすり合わせる必要があることに注意しましょう。
4-4 【ウォーキングカンファレンス】患者さんの参加を目的とする
ウォーキングカンファレンスとは、看護業務の引き継ぎやケアの方針についての話し合いを患者さんのベッドサイドで行うことを指します。
患者さんも治療や看護に積極的に参加してもらうことが主な目的ですが、同時に看護師のOJTやベッドサイドでの安全確認も兼ねています。
患者さんやご家族にケアに関する情報を共有するほか、不安や要望を聞き出すこともウォーキングカンファレンスにおける看護師の重要な仕事の1つです。同室のほかの患者さんやお見舞いに来た方に患者さんの個人情報が漏れないよう気を付けましょう。
4-5 【入院カンファレンス】治療の大きな方針共有を目的とする
入院後、医師・看護師・コメディカル部門が集まり、患者さんの状態や今後の治療方針、退院までの目標などをいろんな方向から検討していきます。
決定事項に基づいて治療が開始され充実した入院生活が送れるように援助していきます。そのためとても大切なカンファレンスです。
4-6 【退院前カンファレンス・地域カンファレンス】スムーズな社会復帰を目的とする
退院前カンファレンスとは入院中の患者さんが退院後にスムーズに社会や家庭に復帰できるよう検討するカンファレンスを指しています。
医師や看護師だけでなく、患者さんにかかわってきた病院スタッフや患者さん本人、ご家族が参加し、場合によってはケアマネジャーや保健師、行政のサービス担当者なども出席します。
入院中の患者さんの状態と退院後の生活について考え、患者さんに必要なフォローについて提案できるよう準備しておきましょう。
4-7 【デスカンファレンス】亡くなった患者さんを振り返りと今後のケアの活用を目的とする
亡くなった患者さんへの看護についてふり返り、今後のケアの参考にする目的で開かれるカンファレンスをデスカンファレンスといいます。
デスカンファレンスでは入院前から入院中の患者さんの経過について整理し、ポイントごとに「看護師としてできたこと」「できなかったこと」「今後の課題」などを議論します。さらに患者さんのご家族へのケア計画を立てることもあるでしょう。
看護師だけでカンファレンスを行う場合もありますが、医師やほかの医療職スタッフと合同で行うことも少なくありません。ほかの職種との考え方のズレを明らかにしたりスタッフの間で気持ちをシェアできたりすることは、デスカンファレンスのメリットの1つといえます。
4-8 【臨床病理カンファレンス】臨床経過と疾患の本態との関連を総合的に理解することを目的とする
デスカンファレンスに関係する会議として臨床病理カンファレンスが挙げられます。
こちらは亡くなった患者さんを担当した臨床医と患者さんの部検を行った病理医が中心となり、患者さんの死因について議論する場であり、基本的にすべての科の医師が参加するカンファレンスとなります。
看護師が参加する機会は多くないかもしれませんが、出席する場合は病棟の垣根を超えて疾患についての理解を深める場であることを意識したうえで参加しましょう。
4-9 【オープンカンファレンス】知識の蓄積・交流を目的とする
オープンカンファレンスはいわゆる講演会や学会、勉強会のような位置づけのカンファレンスです。最先端の技術や機器の使い方を解説したり最新の研究結果について発表したりした後に参加者どうしで議論したり交流を深めたりといった場となります。
多くの場合、開催される病院外からも参加可能です。知識を深める目的で参加するのもよいでしょう。関心があるテーマには積極的に出席してみましょう。
5 延長しがちなカンファレンスを早く終わらせる2つのコツ
医療現場におけるカンファレンスは、延長してしまうことも多いです。限られた時間の中でカンファレンスを充実した時間にするためには、以下の2点が重要です。
①カンファレンス時間を確認し、プレゼン時間を守る!問題点に優先順位をつける!
②クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンを使いこなして、何を相談したいか明確にする!
それぞれについて見ていきましょう。
コツ① 十分な議論の時間を確保すること
カンファレンスで一番重要なのは十分な議論の時間を確保することです。自分のプレゼンに時間をかけ過ぎてはいけません。
カンファレンス時間を確認し、有識者の議論が十分に、かつ、論点が明確になるよう、議論の時間を中心に考えて残った時間を自分のプレゼンの時間とすることが大事です。
時間配分としては、20分で10人の患者さんの相談をする場合、一人当たり2分が割り当てられるという計算になります。割り当てられた時間の7割~8割は議論に宛てたいところですので、この場合の内訳としては時間に余裕をもって、例えばプレゼン30秒、相談時間1分半などとなります。
なお、プレゼンは与えられる時間により情報提供量が変わりますので、何が重要か優先順位を意識すると、どんな時間にも対応できるでしょう。以下に悪い例、良い例を挙げて具体的に解説していきます。
まずは時間と問題点の優先順位を意識していない悪い例を紹介しいます。本来必要な情報は太字で書きますので、太字の個所以外はプレゼンで話す必要が無い部分であるという理解で読み進めていただければと思います。
次に上記事例について、時間と優先順位を意識した良い例を見てみまししょう。下線で引いた個所を中心に、プレゼン時間にあわせて内容を端的にまとめます。
85歳、女性、独居。
圧迫骨折で入院中。
退院後は在宅か転院か相談をしたいです。
85歳、女性。
圧迫骨折で3週間前に入院されました。
退院調整において、独居のため、療養型病院に転院か在宅療養できるか、相談したいです。
85歳の女性。
圧迫骨折で3週間前に入院されました。
現在安静後のリハビリテーションに取り組んでいますが、そろそろ退院を検討しています。
しかし独居のため、在宅調整がつくまでは療養型病院へ転院してから自宅療養がよいか、もしくは本人の希望にそって親戚の助けや介護申請による福祉制度を利用しつつ、すぐ自宅での療養にするか、相談したいです。
時間配分により情報量は変わりますが、10秒のプレゼンであっても、言いたいことは伝わりますね。『独居の患者さんの退院後は在宅でいいのかどうか』ということです。それに対し、20秒、30秒プレゼンは10秒プレゼンという骨格に、肉付けするように情報を大事なことから付け足しています。
コツ② クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンを使いこなす
クローズドクエスチョンとは、「痛いですか、痛くないですか」のように2択で質問をする方法です。複数の答えをあらかじめ用意し、そこから選んでもらうので、答える側の負担が少ない問いかけの方法です。
オープンクエスチョンとは、「どのような痛みですか」のように広く質問する方法です。自由に回答できる質問なので、より深く踏み入って話を伺うことができます。
欲しい結論によってクローズドにするかオープンにするか使い分けが必要です。カンファレンスを早く終わらせることを意識する場合、方針の相談においてクローズドクエスチョンをいかに上手に用いるかがカギとなります。
先程の、圧迫骨折の85歳の独居女性を例にて悪い例・良い例を紹介します。
漠然とした投げかけになっており、これでは端的な議論ができない可能性があります。
良い例は、最後に2つのクローズドクエスチョンがあります。転院か在宅か。他の案があるかないか。こうしたクローズドクエスチョンにより、カンファレンス出席者は2択となりますから答えやすく、端的に検討できます。
もちろん医療の相談なので全てがクローズドクエスチョンで解決はしません。しかし一定の割合でクローズドクエスチョンで解決する相談もあるので、そうしたものは積極的にクローズドクエスチョンを用いて効率よくカンファレンスをすすめることができるのです。
6 まとめ:カンファレンスごとに目的を理解しよう!
「カンファレンス」という言葉は「比較的大規模で正式な会議」という意味合いで捉えられることが一般的ですが、医療分野では「会議」や「話し合い」といった意味で開催されることがほとんどです。医療の現場ではさまざまなカンファレンスが開かれており、看護師はさまざまな種類のカンファレンスに日常的に参加することになるでしょう。
カンファレンスに参加する際にはその目的を理解したうえで出席することが大切です。自分が勤務する職場にはどのようなカンファレンスがあるのかを一度確認しておくとよいでしょう。
ビジネスにおける「カンファレンス」と医療分野における「カンファレンス」の違いを理解し、積極的に参加しましょう。
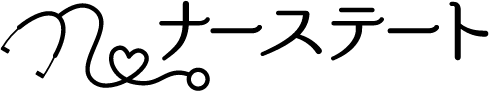



コメント